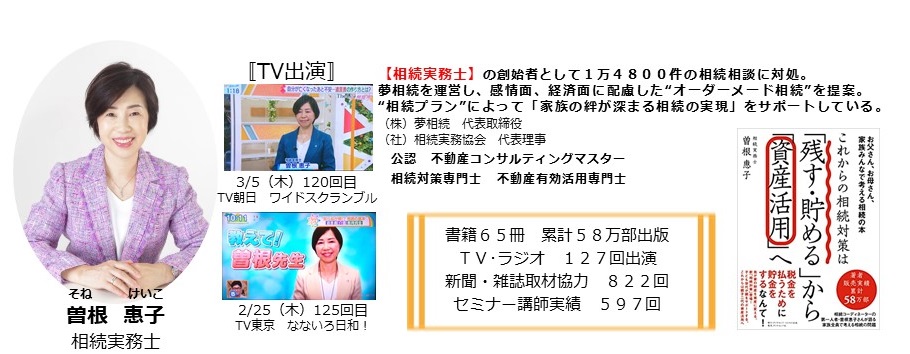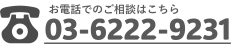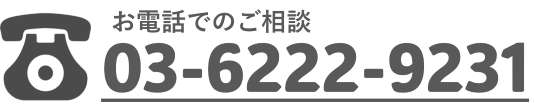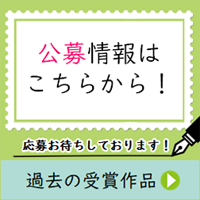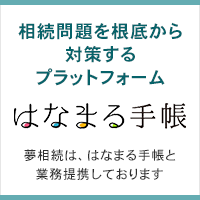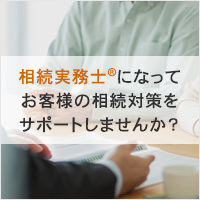事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
広い土地は分筆、別々に相続すれば相続税も下がる!測量は生前にしたい。

■父親は長くないかもと告知された
Fさん(50代男性)から父親(80代)の生前対策のご相談がありました。
父親は長男で、祖父の相続の時に同居する自宅を相続しています。Fさんも長男で祖父母、両親と同居してきました。幸い、勤務先も近く、家から通える範囲です。
すでに祖父母は亡くなりましたが、築50年になる自宅は二世帯にリフォームして現在では両親とFさん夫婦と2人の子どもが生活しています。
父親が80代後半、母親も80代半ば。父親の持病が悪化したことから主治医からそう長くないかもしれないと言われて、いよいよ相続のことが気になり始めたといいます。
■自宅が広い 600坪ある
父親が相続した自宅の土地は約1200坪ありましたが、祖父の相続税を払うために半分を売却して納税するようにしたといいます。それでも自宅の土地は600坪あります。売却した隣地は真ん中に道路を入れて10区角に分割、造成されて、きれいな住宅地になっています。私鉄ながら最寄駅から徒歩5分と近いので、すぐに売れたようで、現在では10軒の住宅となっています。その隣地のF家は600坪に1軒が建っているという、見事な対比となっています。
600坪の真ん中に自宅建物が建っていて、手前に庭があります。道路側は未利用で空き地です。奥の300坪は庭というよりは雑木林のようになっています。
■何も対策をしてこなかった
父親は公務員で真面目に生活して来られて、贅沢をするタイプではありません。
祖父から相続した土地をずっと守ってこられました。手前の空き地は幹線道路沿いにありますので、貸店舗など建ててもいいし、賃貸アパートを建てても需要はある地域ですが、父親は建築費の借金が嫌というタイプで、多くのハウスメーカーから勧められたのですが、頑なにウンといわず、相続税の節税対策はなにもしてこなかったのです。
自宅以外の未了地は自宅と一体の宅地として固定資産税を課税されていますので、年間100万円程の固定資産税を納付しています。所有地からの収入はないため、父親の預金から払っている状況です。
祖父の相続の時に土地を売って納税した経験があるにも関わらず、父親はまったく相続対策をしていません。相続になったらどれくらいの相続税がかかるかも不安だといいます。よって父親の相続プランにつき、委託を頂き、いまからできる対策を提案しました。まずは自宅の土地の評価を確認しました。
■大きな土地は減額できる
父親の財産は土地600坪。面積に路線価を掛けると評価は2億円以上なのですが、500㎡以上の土地で一定の要件に当てはまると「地積規模の大きな宅地の評価減」を適用することができます。宅地として区角割する場合などを想定すると公共用地の負担などがあり、有効宅地が減ることから、面積などの要件に該当すれば計算式に当てはめて算出することができます。
評価の詳細につき、
税理士ともFさんの父親の土地は他の条件も加味することによって38%減の評価になります。
■土地を分筆することで評価を下げることができる
つぎに検討したのは、600坪の土地の活用を想定することです。一帯の土地ながらも、①自宅、②自宅前の未利用地、③奥の雑木林の3つに分けられますので、二次相続で母親が対策できることを前提として、①+②と③を分筆するAパータンと①と②+③を分筆するBパターンを作成、相続する人を分けて、土地の不整形を作り出し、評価を下げる方法を取ります。
不整形になるのはBパターンの方が大きいため、父親の生前に測量、分筆する準備をすることを提案しています。
相続になってから測量、分筆しても同じ効果は得られるのですが、測量・分筆の費用を父親が負担しておくことで、現金は減りますので、それも節税になるのです。
■相続プランの価値
父親はまだご健在ながら、もう大々的な対策ができる余裕がないところ。けれどもFさんが相続プランの委託をされて、夢相続でいろいろなご提案をすることで相続のイメージができ、節税の方法もあることがわかったと喜んでおられます。相続プランの費用もお父さんのお金を使うということで節税になります。
また、母親の二次相続の案も提案していきますので、さらに節税対策が進められますので、さらに安心頂けるよう、継続してコーディネートをさせて頂きます。
■地積規模の大きな宅地の評価減とは
地積規模の大きな宅地の評価減は、日本の土地に関する税制で適用される評価減制度の一つです。この制度は、通常の宅地に比べて面積が広い土地に対して、評価額を減額する仕組みです。これは、地積が広いほど利用価値が限定され、売買や活用が難しい場合があることを考慮した特例措置です。
主な内容
以下に制度の要点をまとめます。
1.対象となる土地
・面積が500㎡以上の宅地であること。
・一般的に市街化区域や市街化調整区域に所在し、住宅地としての利用価値がある場合。
・土地の形状や位置が評価減の対象として適切である場合。
2.評価減の計算方法
地積規模の大きな宅地に対しては、以下のように評価額を算出します。
1.宅地としての評価額を計算(通常の宅地評価額を基準)。
2.規模に応じた減額率を適用。
・減額率は土地の面積や立地条件(市街地や郊外など)によって異なります。
・面積が広くなるほど減額率が高くなる傾向があります。
3.適用範囲の制限
小規模宅地等の特例とは併用できないケースが多いです。
例えば、相続税の課税評価において小規模宅地の特例を利用している場合、地積規模の大きな宅地としての評価減が適用されないことがあります。
4.目的
この制度の目的は、以下の点に対応するためです。
・広大な宅地の利用価値が相対的に低いことを反映。
・広い土地を持つ所有者に過度な税負担を課さないようにする。
・市場価値に沿った公平な課税を実現。
5.具体的な減額率
例えば、評価額を面積に応じて次のように調整します。
・500㎡超〜1,000㎡以下の部分に一定の減額率を適用。
・1,000㎡超〜2,000㎡以下の部分にはさらに大きな減額率を適用。
■一体の土地を分筆、所有者を分けることのメリット
一体の土地を分筆し、所有者を分けることで相続税が下がる理由は、土地の評価額の計算方法や適用される税制上の特例が変わるためです。以下で理由を整理して説明します。
1.土地評価の計算基準が変わる
・土地は一体として評価が行われる
一体の土地として評価される場合、広大な土地は「整形された大きな土地」として扱われ、全体的に高い評価額が付くことがあります。これを**「一筆の土地」**として税評価するためです。
・分筆で小規模な土地として評価される
分筆することで、土地の評価が分割され、個々の区画が相対的に小さくなるため、周辺の取引価格や路線価に応じた評価額が低下する場合があります。
2.「広大地評価」の適用が変わる
・広大地評価の非適用エリアを分ける
分筆によって、「開発適用性のある土地」と「そうでない土地」を分けることで、一部の土地が広大地評価を受け、評価額が下がる可能性があります。
・広大地評価が適用されると、評価額が最大30%~50%減少する場合があります。
3.小規模宅地等の特例の適用
・特例の対象土地を分筆で明確化
小規模宅地等の特例では、一定面積までの土地が大幅に評価減されます。例えば:
・住宅用地:330㎡まで80%減額
・事業用地:400㎡まで80%減額
一体の土地だと、この面積上限を超える部分が高額評価されますが、分筆して土地所有者を分けることで、複数人がそれぞれ特例を受けられる場合があります。
4.合計税額の分散効果
・分割による課税対象の分散
土地を分筆し、所有者を複数に分けることで、個々の相続人の課税対象が減少し、結果として適用される税率が低くなる可能性があります。
相続税は累進課税(課税額が増えると税率も上がる)です。財産を分散させることで、課税額全体を下げる効果が期待できます。
5.利便性・収益性の変化
・分筆後の土地は、より収益性が高い部分(例えば住宅地や事業用地)とそうでない部分(雑木林や不整形地)に分けやすくなります。
・収益性が低い土地として評価される部分が増えるため、評価額全体を引き下げることが可能です。
最初のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】
コラム執筆