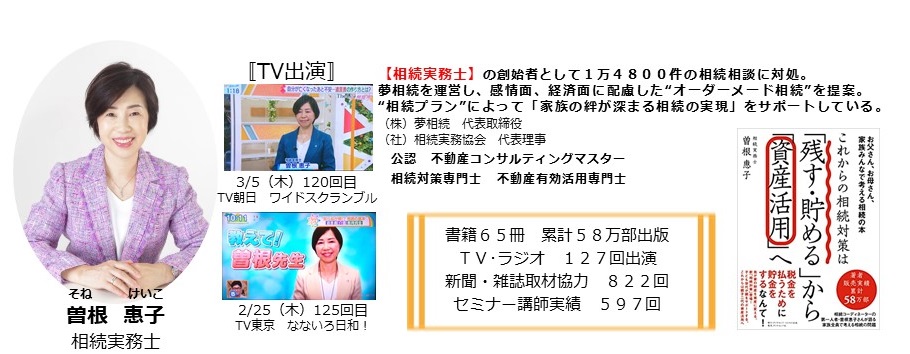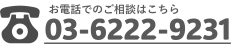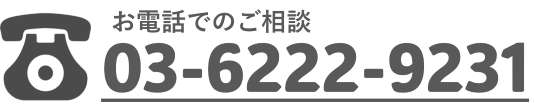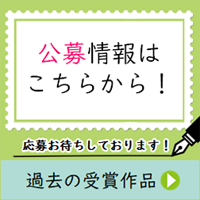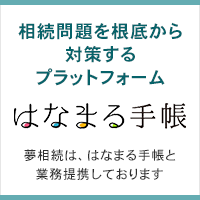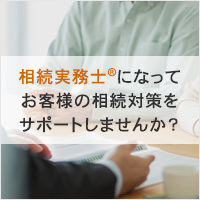事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
跡継ぎが自分でないと。予定通りでないと家の問題は感情論。根が深い。

■家の跡継ぎ問題は感情論。根が深い。
家族の歴史とともに受け継がれてきた土地や財産。しかし、その継承の過程で発生する感情的な衝突は、しばしば家族関係に深い亀裂を生じさせます。特に、跡継ぎが「予定通りではない」とき、あるいは「自分が選ばれなかった」とき、そこに生じる感情は非常に根深いものとなります。相談に来られたS家の実際の相続問題のケースを交えながら、跡継ぎ問題の本質と、その解決策について考えてみます。
■1.跡継ぎ問題の背景にあるもの
多くの資産家の家庭では、財産を守ることを目的として、長男や特定の子供を「跡継ぎ」として育てることが一般的です。しかし、時代の変化とともに、必ずしも家業を継ぐ意志がない、または能力的に適任ではない場合もあります。そのような状況で、別の子供が家を継ぐことになると、他の家族からの反発を招くことが少なくありません。
また、財産分与の公平性に対する認識の違いも、家族間の争いを引き起こします。「自分は長年家業を支えてきたのに、なぜ平等に分けられるのか」「兄は十分な財産をもらっているのに、なぜさらに優遇されるのか」といった不満が積み重なることで、相続の場面で感情的な対立が顕在化するのです。
■2.具体的な事例:S家のケース
今回の事例では、土地持ち資産家であるS家において、長男ではなく次男が跡継ぎとして選ばれたことが家族内の大きな争いを生む原因となりました。
S家は代々多くの土地を所有する地主の家系で農家でもあります。Sさんの父親は長男で祖父から20か所以上の市街化区域の土地と農地を相続し、財産評価は10億円以上。地方都市ながら、近くに大学があり、所有する土地に賃貸アパートや寮を建てて、賃貸事業をしており、安定的な収入があります。
父親の相続人は、母親と長男、長女、次女、次男のSさんの5人です。長男は跡取りだと言われて祖父母や両親から育てられたにも関わらず、結婚した妻にはそれが重圧だったよう。同居したものの、両親との関係が悪化し、同居を解消。長男は家や両親よりも妻を優先せざるを得ない状況のため、最良の選択として選択されたのですが、妻を追い込んだのは両親や妹、弟たちだと家族を責めるようになりました。
長男家族が同居を解消したあと、両親の強い希望により、次男のSさん家族が跡取りとして同居を始めましたので、両親も姉たちも安心してくれているのですが、長男だけはそれが許せないようです。長男は自分が家を継ぐ跡取りではないということが現実になると、弟に対して嫌がらせをするまでになりました。
昨年、父親が亡くなり、遺言書があるものの、その内容で長男が納得しないため、Sさんが相談に来られたのでした。
当社では長男にも理解が得られる遺産分割を提案し、長男をはじめ、母親、姉たちも同意が得られて、遺産分割協議書を作成することができるめどを作ることができました。父親の相続手続きは終えられそうですが、母親の二次相続でも今回と同様に長男が難色を示すことが想定されます。母親は80代ですが、まだ何年も先の相続になると、その間の長男がまた、嫌がらせをしなくもありません。
よって、母親には遺言書が必須ですが、その前に長男に財産の前渡しとして現金か不動産を贈与して、将来の相続でまた感情的な問題にならないよう、生前に相続問題を解決しておくことをご提案しました。長男に満足のいく財産を先渡しし、遺留分放棄をしておいてもらうことで、母親の相続時には遺言書のみでスムーズな手続きをすることを想定しています。
今回のS家のように、代々の土地を多く所有しておられる資産家は「家を継ぐ」ことを優先する傾向にあることで、家族の課題を抱えていくこともあると痛感した事例です。できるだけ家族でコミュニケーションを取り、不満が残らないような選択をしていく必要があります。
■3.感情論が相続問題をこじらせる理由
相続に関する法律は明確ですが、家族間の感情はそう簡単に整理できるものではありません。特に「家を守るべき」「長男が継ぐべき」といった固定観念が根強い家庭では、法律だけでは解決できない問題が山積しています。
本来、相続は「財産の分け方」だけではなく、「家族の未来をどうするか」という視点を持つべきです。しかし、感情的な争いが激化すると、「自分が損をした」「あの人が得をした」といった視点に偏りがちです。その結果、本来スムーズに進むはずの手続きが滞り、家族関係の修復が困難になってしまいます。
■4.感情の対処と解決策
では、このような問題をどのように解決すればよいのでしょうか?
- 感情の整理と対話の場を設ける 相続問題が発生する前に、家族全員が話し合える場を設けることが重要です。遺産分割についての希望や、家族間の感情を事前に共有することで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
- 専門家の介入 感情論がこじれてしまった場合は、弁護士や相続実務士のような第三者に仲裁を依頼するのも有効です。専門家が客観的な視点からアドバイスをすることで、冷静な判断が可能となります。
- 遺言書の活用 遺言書があれば、相続に関する争いを最小限に抑えることができます。ただし、一方的な内容ではなく、家族が納得できる形での作成が望まれます。
- 資産活用の視点を持つ 財産は活用してこそ意味があるものです。相続を機に、単なる財産分与ではなく、家族全体の利益を考えた資産運用の方法を模索することが大切です。
■専門家のサポートが必要
相続問題は、法律だけでなく、家族の感情や価値観が大きく影響します。跡継ぎが自分でないと分かったとき、あるいは予定通りでないとき、家族内での対立は避けられないこともあります。しかし、感情論だけで問題を進めると、最終的には全員が損をする結果になりかねません。
相続は「争続」ではなく、「家族の未来を築く機会」と捉えることが重要です。そのためには、冷静な対話、専門家の介入、そして家族全体の利益を考えた資産活用が求められます。
S家の事例のように、深い感情のしこりが残ることもありますが、最終的に家族が納得できる形で解決策を見出すことができれば、それが最善の相続となるのではないでしょうか。
■まとめ 土地持ち資産家における「跡継ぎ」制度の是非
肯定的な側面
土地持ち資産家では、代々受け継がれてきた土地や家業を守ることが重要視されます。そのため、長男や長女、あるいは養子を「跡継ぎ」として育て、財産の維持・管理を任せる慣習が根付いています。この仕組みにより、土地の分散を防ぎ、資産の価値を維持することが可能となります。また、家業がある場合は、一貫した経営方針を貫くことができ、地域社会との関係も維持しやすいといえます。
さらに、跡継ぎとして育てられることで、責任感や経営者としての意識が早くから培われる点もメリットの一つだといえます。財産の管理には専門的な知識や経験が求められるため、計画的な承継がなされることで、スムーズな世代交代が可能になるのです。
否定的な側面
一方で、跡継ぎ制度にはいくつかの問題点もあのます。まず、本人の適性が考慮されず、「長男だから」「長女だから」といった理由だけで後継者に指名されるケースが多いのが現状です。その結果、資産を適切に管理できず、むしろ家業が衰退する事態を招くこともあることでしょう。
また、跡継ぎを強要されることで、本人の自由な人生設計が制限される場合があるかもしれません。自分の夢や適性とは異なる道を歩まざるを得ず、精神的な負担が大きくなることも少なくないといえます。特に現代では、多様な生き方が求められる時代となり、「家を守るために生きる」という価値観に縛られることへの反発も増えているかもしれません。
結論
土地持ち資産家における跡継ぎ制度は、資産の維持や経営の継続において一定の合理性がありますが、時代の変化に合わせて柔軟に対応する必要があります。適性や本人の意思を尊重し、専門家のアドバイスを受けながら、より合理的な資産承継の方法を模索することが求められる時代となりました。家族全体での話し合いや、第三者の意見を取り入れることで、より良い跡継ぎのあり方を考えていくべきではないでしょうか。
最初のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】
コラム執筆